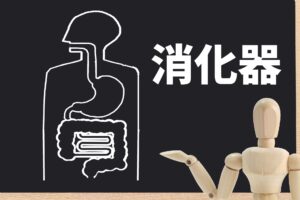大人だけではない!子供にも起こる肩こり!

最近まで、肩こりは中高年特有の問題と思われていましたが、実際には子供たちにも広がっていることをご存知でしょうか?
現代のライフスタイルは大人だけでなく子供たちにも大きな影響を与え、日常的な姿勢の悪化や運動不足が深刻な健康問題となっています。
特にデジタル機器の普及により、猫背、巻き肩、骨盤の傾きといった姿勢不良が定着し、それが慢性的な肩こりや身体の不調につながっています。
この記事では、肩こりが子供にも増えている理由、日常生活の改善ポイント、姿勢を整えるための具体的な方法を詳しくお伝えします。
是非最後までご覧ください。

子供にも肩こりが増えている現実
かつては、肩こりといえば中高年以降の大人に多く見られる不調のひとつというイメージが一般的でした。しかし、近年の調査や報道を通して明らかになってきたのは、「肩こりは子供にも起こる」という事実です。ゴールデンウイーク中の「こどもの日」に合わせて発表された記事では、ここ数年で肩こりを訴える子供の数が増加しており、しかもその傾向が年々低年齢化しているということが取り上げられていました。
肩がこるという症状は、加齢に伴う身体の変化だけが原因ではなく、姿勢、生活習慣、環境の変化によって誰にでも起こりうるものです。そのため、肩こりは年齢によって区別されるような症状ではなく、子供から高齢者まで幅広い世代に共通して見られる身体の不調と言えます。
実際に、小学生の段階で「肩が重い」「肩が痛い」「首や背中がだるい」といった症状を訴えるケースは決して珍しくなくなってきました。大人になると、デスクワーク、スマートフォンの長時間使用、慢性的な運動不足、質の低い睡眠、栄養の偏った食事など、肩こりの原因として考えられる要因が多く存在することに気がつくようになります。しかし子供の場合、これらの原因に対する理解や対処法を身につける機会が少ないまま、肩こりが「普通のこと」として日常に定着してしまうリスクがあります。
つまり、子供の頃に「肩がこるのは当たり前」と感じたまま成長してしまうと、大人になってからもその状態が慢性化し、自分の身体の状態を疑うことすらなくなってしまう可能性があります。これが非常に問題なのは、そうした子供たちが将来的に肩こりによる集中力の低下、イライラ、学業や仕事のパフォーマンスへの悪影響を抱え続けることになりかねないからです。
では、なぜ現代の子供たちに肩こりが増えているのでしょうか。その背景には、生活環境の大きな変化、特にデジタルデバイスの急速な普及があります。スマートフォン、タブレット、パソコンといった機器は、かつては大人の道具というイメージが強かったものの、今では子供たちの手の届くところに日常的に存在するようになっています。
デジタル機器を巧みに使いこなし、ネット検索で知識を得たり、SNSで友達と交流したり、動画視聴やゲームに夢中になったりする子供たちの姿は、今やごく当たり前の風景となりました。学校でもICT教育が進み、授業でタブレットを使う機会が増えているほか、家庭でも自分専用のスマートフォンやキッズケータイを持つ子供が年々増加しています。
実際、NTTドコモの研究機関である「モバイル社会研究所」が2024年11月に全国の小中学生とその保護者1,300人を対象に実施した調査によると、小学高学年におけるスマートフォンの所有率はすでに52%と半数を超えており、この傾向は今後さらに加速していくことが予想されています。
スマートフォンで子供たちが主に行っていることとしては、「ゲーム」や「動画視聴」が圧倒的に多く、いずれも画面を長時間見続けるという共通点があります。これにより、猫背ぎみな姿勢が固定され、首から肩、背中にかけての筋肉に常に負担がかかるようになります。しかもこの状態が日常的に、しかも長時間続くため、筋肉がこわばって血行が悪くなり、結果として肩こりを引き起こしてしまうのです。
こうした現象は、大人が長時間のデスクワークやPC作業で肩こりになるのとまったく同じメカニズムです。つまり、子供たちは年齢が若くても、身体に起こっていることは大人と同様であり、むしろ発育途中の身体にとってはより大きな負担になっている可能性すらあります。
私たち大人が今すぐにできることは、子供たちの姿勢や生活習慣に対して意識を向け、適切な指導とサポートを行うことです。適度な運動習慣を取り入れたり、スマホやタブレットの使用時間に制限を設けたり、画面を見るときの姿勢を整えたりすることで、肩こりの予防につなげることができます。
肩こりは決して「年のせい」ではなく、「現代社会の生活スタイル」に大きく関わっている問題であるということを私たちは改めて認識する必要があるでしょう。そして、それは未来ある子供たちの健康を守るためにも、今から真剣に取り組むべき課題なのです。
座りすぎ・運動不足への日常的な対策の必要性
大人は現代社会において、仕事上でパソコンを使うことが多くなり、朝から晩までデスクワークを続けるということが珍しくありません。そのため、長時間にわたって座り続けることが日常化し、結果として運動不足に陥ってしまっています。運動不足は身体の代謝を悪化させ、筋力の低下や血行不良を引き起こし、さらには慢性的な肩こりや腰痛の原因にもなります。
一方で、子供の場合も、大人ほど長時間ではないにしても、学校の授業時間は座っていることが基本となります。前述したように最近ではデジタル化が進み、授業でタブレットやパソコンを使った学習が増えてきており、画面を見る時間も長くなっています。これにより、視覚の疲れや姿勢の悪化、筋肉の緊張といった身体への負担も増加します。
地域差や学校の状況にもよりますが、放課後は塾や習い事に通う子供も多く、さらに座ったままの学習時間が増える傾向にあります。授業後、座ったままの学習を継続することは子供の身体にも精神的にも疲労を蓄積させます。さらに、自宅でのリラックス方法として、スマートフォンやタブレットで動画視聴やゲームを楽しむことも一般的になりつつあります。ゲームの中には身体を動かすものも存在しますが、画面を眺めながら同じ姿勢を取り続けることが多く、実際には身体が動かないケースがほとんどです。
また、小学生の場合、特に注目されるのがランドセルの重さです。教科書、ノート、筆記用具に加えて、近年ではデジタル端末を持ち運ぶことも増えてきました。これによりランドセルがさらに重くなり、低学年の子供にとっては非常に大きな負担となっています。ランドセルが体格に合っていない場合、その重さと大きさが肩や背中、腰に不自然な圧迫を与え、慢性的な肩こりや腰痛、姿勢の悪化を招く可能性があります。これがいわゆる「ランドセル症候群」と呼ばれる問題で、通学自体が苦痛になり、学校生活への意欲が低下することも少なくありません。
さらに、学校では通常の授業以外にイベントや行事もあり、その際には特別な持ち物が増え、さらに荷物が重くなることがあります。大人でもノートパソコンや資料などを運ぶことで身体への負担が増えるのと同様に、子供にもこうした荷物の重さが身体的な負担となって蓄積します。
したがって、大人も子供も、日常生活において座る時間が長くなり、運動不足や身体への過度な負担が増えている状況にあると言えます。これを改善するためには、意識的に適度な運動を取り入れたり、身体に合った荷物の選択や、適切な休憩時間を設けるなど、日常的な配慮が必要です。
猫背姿勢が子供の身体に与える影響と改善への工夫
肩こりが起きやすい姿勢としてよく知られているのが「猫背」の姿勢です。現代の小学校での状況は異なるかもしれませんが、かつては姿勢が悪いまま授業を受けていると教師から「背筋を伸ばしなさい」と注意される場面が頻繁にありました。
しかし、まだ筋力の十分に発達していない小学生にとって、長時間にわたって正しい姿勢を維持し続けることは非常に難しく、むしろ身体に負担をかけることにもなりかねません。むしろ、自然に身体をもぞもぞと動かす方が、筋肉の血流やリンパの流れを促進する効果があるという意見もあります。実際、多くの子供がじっと座り続けられずに落ち着きなく動いてしまうのは、本能的に血液循環を促そうとしている可能性もあります。
それでもやはり、長時間悪い姿勢で座り続けることは、筋肉への負担を増大させます。これは大人でも子供でも変わりありません。筋肉の構造や働きは年齢に関係なく同じため、特に肩や首の筋肉に長時間の負荷がかかれば、その部位に疲労や痛みが蓄積します。デスクワークで長時間パソコンを操作したり、スマートフォンを長く見続けたり、ゲームをプレイするために背中を丸めて何時間も座っていたりすることは、身体にとって非常に負担となります。
特に子供の身体は成長過程にあり、骨格や筋肉の形成が完全に完成するのは一般的に18歳頃と言われています。この成長期に悪い姿勢が定着してしまうと、将来的にも慢性的な肩こりや姿勢の悪化が固定されやすくなります。したがって、成長期の子供にとっては、運動習慣をしっかりと身につけ、適度な筋力をつけることで自然に良い姿勢を保つ能力を高めることが理想です。家庭や学校でも、適切な休憩を取ったり、授業中に軽いストレッチを導入したりすることで、身体の負担を軽減する工夫をしていくことが必要です。
肩甲骨の位置が肩こりに与える影響と筋肉の役割
理想的な姿勢と言うと、隅々まで細かくこだわることができますが、肩こりに関してはまず肩甲骨の位置と身体への負担を考えていくことが大切です。そもそも身体全体の姿勢というのは、骨盤の傾きや背骨の弯曲の度合いといった骨格の配列によって決まります。この骨格の配列が理想的な位置に整えられていると、姿勢のバランスが良好となり、筋肉への余分な負担が減り、結果としてエネルギーの消費も最小限に抑えられます。
特に肩甲骨は背中の左右に位置し、理想的な肩甲骨の配置としては、背骨から肩甲骨までの幅が約7センチ程度であることが挙げられます。肩甲骨が背骨に近すぎると、背面の筋肉が窮屈になりすぎ、逆に離れすぎると肩甲骨は前方へ引っ張られてしまいます。これは座っているときにありがちな猫背姿勢でよく見られる現象です。
肩甲骨は、肋骨や背骨、さらに頭蓋骨の後頭部までつながる筋肉と連結しています。加えて、腕の骨である上腕骨とも密接につながり、腕の位置や動きによって肩甲骨自体も動かされます。例えば、スマートフォンやパソコンを操作する際は、腕が前方に位置するため肩甲骨も前方へ動きます。しかし、このまま前方へ動き続ければ肩甲骨も腕も前方に大きく逸脱してしまいます。
それを防ぐのが筋肉の働きです。前方への肩甲骨の動きを制御するのは主に僧帽筋や菱形筋といった筋肉です。これらの筋肉は、肩甲骨を適切な位置で保つために、継続的に筋力を発揮しています。僧帽筋は肩甲骨の上部から背中上部に広がる大きな筋肉で、肩こりが起きると揉んでもらいたくなる代表的な筋肉です。一方の菱形筋は、肩甲骨の内側から背骨に向かって伸びている筋肉で、背中が硬いと感じる部分にあります。
前方へ動こうとする腕の重さを僧帽筋や菱形筋がブレーキのように止めるため、これらの筋肉には常に負担がかかり、結果として肩こりやだるさが生じることになります。一方、肩甲骨を前方に引っ張る筋肉には大胸筋、小胸筋、前鋸筋などがあります。これらの筋肉は前方へ向かう姿勢の際には、筋肉の長さ自体は縮まりますが、前かがみの状態では筋力をそれほど発揮せず、むしろ重力に任せて短くなってしまう傾向にあります。この状態が続くことで肩甲骨が前方に固定されてしまい、いわゆる「巻き肩」と呼ばれる姿勢が定着してしまうことがあります。
日常的に肩甲骨周囲を意識したストレッチや筋力トレーニングを取り入れることで、姿勢改善と肩こりの軽減につながるでしょう。
骨盤の傾きと姿勢の関係性!肩こり予防と健康維持のポイント
背中が丸まってしまう原因には、肩甲骨の位置だけでなく、背骨の土台である骨盤の角度や位置も深く関係しています。骨盤には「前傾」と「後傾」と呼ばれる前後方向への角度があり、この傾きが姿勢に大きく影響します。
骨盤が後傾すると、背骨は下方向に引き下げられ、それに伴って背中は丸まりやすくなります。また背骨の自然な弯曲も減少してしまい、背中が平坦化するなどして、姿勢全体が崩れてしまうこともあります。一方、骨盤が前傾しすぎても背中が過剰に反り返り、結果として猫背のように背中が丸く見えるケースがあります。しかし、日常生活で楽な姿勢として一般的に選ばれやすいのは、骨盤が後傾した姿勢であり、これは座っているときに無意識のうちにとってしまう姿勢です。
特に、椅子やソファに深く腰掛けたり、床にあぐらをかいて座った状態でスマートフォンやタブレットを使用しているときには、意識的に骨盤を前傾させ、いわゆる「骨盤を立てる」姿勢を維持することはなかなか難しいことです。多くの場合、骨盤は後ろに倒れやすくなり、自然と背中が丸くなり、頭も前方へと傾いてしまいます。
成長期にある子供の場合、このように背中が丸まった姿勢が日常的に定着すると、骨格や筋肉の発達にも影響が出ます。背骨や骨盤の正しい位置が固定されず、身体全体のバランスが乱れるため、スポーツや運動を行う際にも腰や膝に余計な負担がかかりやすくなり、怪我のリスクが高まることもあります。
また、大人であっても同様で、デスクワークや日常生活において適切な椅子の高さや机の高さを選ぶことが非常に重要になります。椅子や机が合っていないと、無意識に猫背になりやすく、首や肩に過度な負担がかかり、慢性的な肩こりや腰痛の原因となります。スマートフォンやタブレットを使用するときも、画面を目の高さに近づけるための専用スタンドや適切な置き方を工夫し、頭が下がり過ぎたり、目線が下がり過ぎたりしないよう注意することが望ましいです。
そして肩こり改善を目指すだけでなく、身体を積極的に動かすことは、筋肉、関節、神経系の働きを向上させることにつながります。定期的に身体を動かすことで、筋力、柔軟性、バランス感覚、協調性といった身体機能全般が高まり、日常生活の快適性や運動能力の向上にもつながるでしょう。日頃からストレッチ、ウォーキング、適度な筋力トレーニングなどを習慣化することが、身体全体の健康を保つためにも非常に効果的なアプローチです。

まとめ
肩こりの問題は年齢に関係なく、現代社会のライフスタイルが引き起こしています。
子供のうちから肩こりや姿勢の悪さを放置すると、将来の健康や生活の質に大きな影響を与えます。
大人が率先して適切な姿勢や日常的な運動習慣を取り入れることで、子供たちも自然に健康的なライフスタイルを学ぶことができます。
今日から小さな一歩を踏み出してみませんか?
TRANSCENDでは、一人ひとりの状況に合わせて適したメニューを組んでいます。
通う頻度についても月2回、月4回、月8回の3つのプランから選択できるので、お気軽にご相談ください。