糖質との付き合い方で身体が変わる-代謝・脳・ダイエットを科学的に見直す-
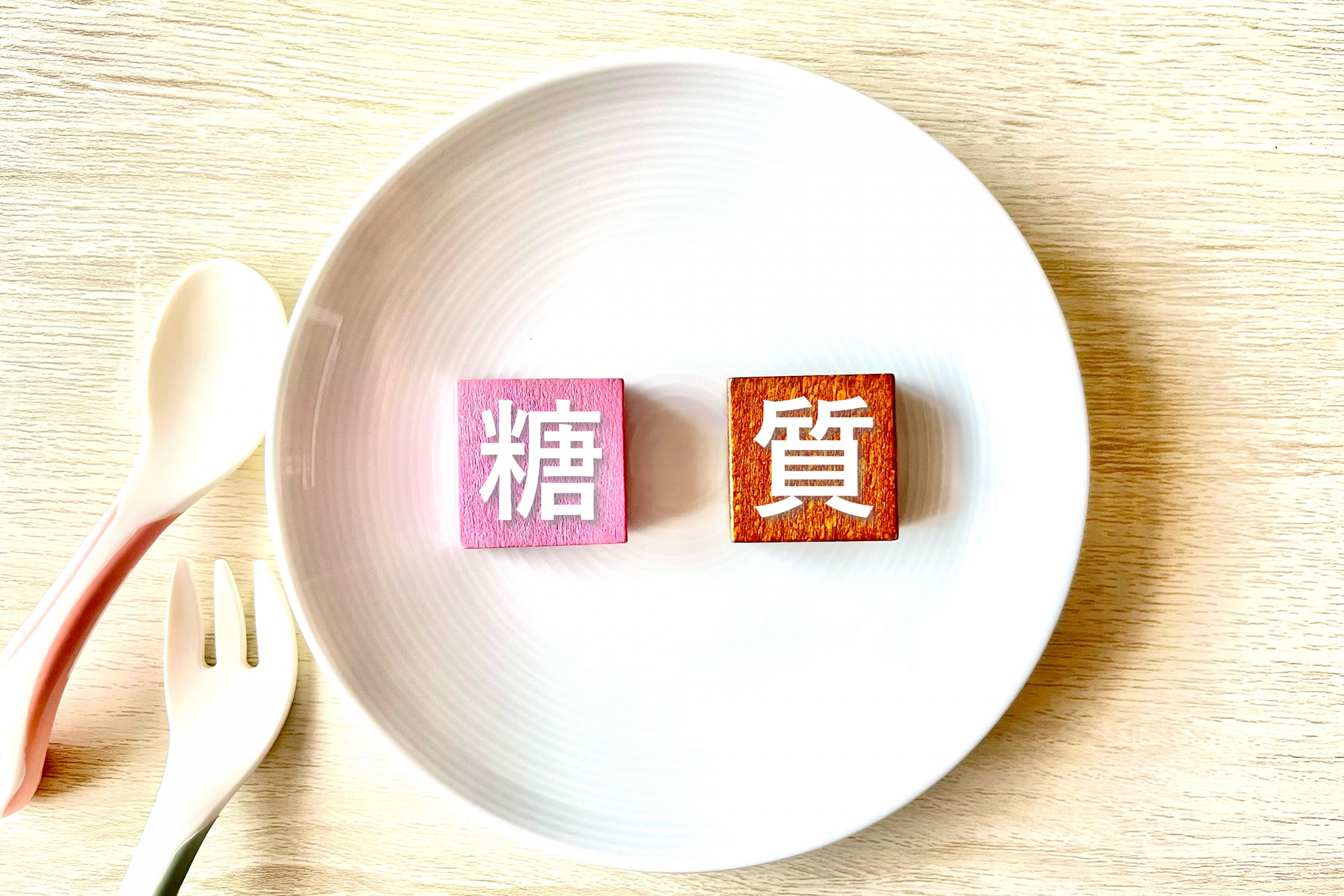
現代では、「糖質を控える」という健康意識がすっかり定着しつつあります。
実際、糖質制限はダイエットや血糖コントロールの手段として注目され、手軽に体重が落ちやすいというメリットから、多くの人に選ばれてきました。
しかし、「糖質を減らせば痩せる」といった単純な図式だけで語るには、私たちの身体はあまりにも複雑です。
糖質の消化・吸収・代謝、脳への影響、ホルモンとの関係、筋肉とのバランス。
糖質との付き合い方を誤れば、短期的には痩せても、長期的には代謝や健康にリスクをもたらすこともあるのです。
この記事では、糖質の基礎知識、糖質制限の仕組み、そしてケトジェニックダイエットの効果と注意点など詳しく解説していきます。
是非最後までご覧ください。

現代の食と健康を支える「糖質制限」その仕組みと身体への影響
糖質制限という食事法が広く世の中に知られるようになってから、すでに数年の月日が経ちました。
現在では、私たちが日常的に目にする多くの食品に「糖質オフ」や「糖類ゼロ」といった表示がなされ、コンビニやスーパー、ドラッグストアでもそれらの製品がごく当たり前に並んでいます。今や「糖質を制限する」「糖質を気にする」といった行為自体が、まるで現代人にとって常識的で標準的な健康意識の一部になってきていると感じられます。
糖質制限と聞くと、ダイエットやボディメイクを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。
実際、糖質の摂取量を抑えることで体重が落ちたり、体脂肪が減少したりと、比較的短期間で目に見える結果が得られやすいことから、世代や性別を問わず多くの人が関心を寄せています。特に、運動や筋力トレーニングを日常的に行っている人にとっては、「糖質を減らしながらも筋肉量を維持、あるいは増加させることができるのか?」という点が大きなテーマとなっています。
では、糖質を制限することによって、私たちの身体の内部では一体どのような変化が起きているのでしょうか?
糖質の摂取が少なくなると、体内ではエネルギー源をグルコース(ブドウ糖)ではなく、脂肪やたんぱく質から得られる「ケトン体」にシフトするという適応反応が始まります。この代謝の変化を「ケトーシス」と呼びますが、これは人間の身体が進化の過程で備えてきた自然なエネルギー代謝システムのひとつです。つまり、糖質を取らずとも、人間は脂肪を分解して必要なエネルギーを作り出せるというわけです。
この代謝の変化により、余分な体脂肪を燃やしやすい状態が生まれ、同時にインスリンの分泌も穏やかになるため、血糖値の乱高下が抑えられ、結果として体調の安定や食欲のコントロールがしやすくなるというメリットも期待できます。
糖質制限はあくまで手段の一つにすぎませんが、身体の反応や目的に応じて上手に取り入れることで、脂肪を減らし、筋肉量をキープしながら理想の体型に近づける可能性を持った方法です。もちろん、極端な制限や個人差に配慮することも重要ですが、「糖質を制限することで何が変わるのか」を知ることは、これからの食生活やトレーニング設計において大いに役立つでしょう。
炭水化物・糖質・糖類の違いと脳への影響について
私たちが日常的に口にする「糖質」や「糖類」という言葉は、健康やダイエット、栄養管理の分野では非常に重要なキーワードとなっています。しかし、これらの用語の意味を正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。実は「糖」という言葉の中には、私たちが思っている以上に多くの成分や分類が含まれています。
まず、最も大きな分類である「炭水化物」は、「糖質」と「食物繊維」という2つの成分に分けられます。つまり、炭水化物=糖質+食物繊維という構造です。このうち、糖質は人のエネルギー源として体内で利用されやすい成分である一方、食物繊維はエネルギーにはなりにくいが腸内環境を整える役割を担っています。
さらに、「糖質」の中には「多糖類(デンプンなど)」「糖アルコール(エリスリトールやキシリトールなど)」「その他の糖質」といった複数の成分が含まれます。加えて、「糖類」と呼ばれるのはその中でも特に構造が単純なもの、つまり「単糖類(ブドウ糖、果糖)」と「二糖類(砂糖、乳糖)」のことを指します。
このように、「糖質」と「糖類」は似ているようでいて異なるものであり、糖類は糖質の中の一部に過ぎません。ダイエット食品などに表示される「糖類ゼロ」は、あくまで単糖類や二糖類が含まれていないという意味であり、糖質が全くゼロというわけではないことに注意が必要です。
そして、「糖質」と聞いて多くの人が真っ先に思い浮かべるのが、ダイエットの敵のようなイメージかもしれません。しかし糖質は、本来人間の生命活動に欠かせない重要な栄養素のひとつです。特に、脳はブドウ糖を主なエネルギー源として使っているため、糖質の摂取量が極端に減ると脳の働きに影響が出る可能性があるのです。
人間の脳は、1日に消費するエネルギーのうち、実に約20〜25%を占めるほど大量のエネルギーを必要としています。その大半はブドウ糖によってまかなわれています。ブドウ糖は「単糖類」のひとつであり、私たちがご飯、パン、麺類といった炭水化物を食べたとき、体内で分解されてブドウ糖として吸収され、血液を通じて脳に運ばれます。
ここで重要なのは、「炭水化物・糖質・糖類を完全にカットするような極端な糖質制限を行うと、脳が必要とするブドウ糖を摂取できなくなる可能性がある」という点です。身体は脂肪やたんぱく質からもケトン体など代替エネルギーを作り出すことができますが、それには適応期間が必要であり、すべての人がスムーズに対応できるわけではありません。
また、ケトン体がある程度脳のエネルギー源として働けるとはいえ、ブドウ糖のように即効性があるわけではなく、集中力の低下や頭がボーッとする、イライラする、思考が鈍くなるといった症状が出ることもあります。これらは糖質不足による脳機能の低下のサインとも言えるでしょう。
したがって、糖質を制限する際には、単に「糖を減らせば痩せる」「糖類ゼロのものを選べばよい」という短絡的な判断ではなく、自分の活動量やライフスタイル、仕事や勉強への影響も含めて、バランスよく取り組むことが大切です。
糖質は「悪者」ではありません。必要な量を、必要なタイミングで、質の良い糖質から適切に摂ることが、健康的な身体と脳の働きを支える大切な要素なのです。
糖質の消化・吸収とエネルギー代謝の仕組み
私たちが毎日の食事から摂取する「糖質」は、身体にとって非常に重要なエネルギー源のひとつです。ご飯、パン、麺類、果物など、糖質はさまざまな食品に含まれており、日常的に摂ることがごく自然となっています。しかし、この糖質が体内でどのように処理され、最終的に脂肪として蓄えられるまでのプロセスを正しく理解している人は案外少ないかもしれません。
まず、糖質は口に入った瞬間から体内での消化が始まります。唾液中には「アミラーゼ」という酵素が含まれており、これが炭水化物(特にでんぷん)を分解し、より小さな糖にしていきます。次に、胃を経て小腸に到達すると、膵液や腸液といった消化液の働きにより、さらに細かく分解され、最終的には「ブドウ糖(グルコース)」などの単糖類として吸収される状態になります。
小腸で吸収されたブドウ糖は、そのまま血液中に入り、まず肝臓へと運ばれます。肝臓は体内の“代謝の司令塔”とも言える臓器で、必要に応じてブドウ糖を全身の細胞に送り出し、エネルギーとして使われるよう調整を行います。脳、筋肉、心臓など、日々活動している臓器や器官はこのブドウ糖を燃料にして働いています。
しかし、身体が一度に使用できるエネルギーには限りがあります。食後に急激に増えたブドウ糖が細胞で使い切れない場合、身体は「余った糖」を一時的に保存する仕組みを持っています。それが「グリコーゲン」という形です。グリコーゲンはブドウ糖が多数結合した貯蔵用の糖分子で、主に肝臓や筋肉の中に蓄えられます。運動時や食事がとれない空腹時には、この貯蔵されたグリコーゲンが再び分解されてエネルギー源として活用されます。
ところが、肝臓や筋肉に貯蔵できるグリコーゲンの量には限界があります。一般的には、肝臓には約100g、筋肉には個人差がありますが約300〜400gほどのグリコーゲンを蓄えることができるとされています。これを超える量の糖質を摂取してしまうと、身体は「余剰分」を別の形に変えて保存しようとします。その変換先が「中性脂肪」です。つまり、過剰な糖質は脂肪へと変換され、皮下脂肪や内臓脂肪として体内に蓄積されることになるのです。
さらに、糖質の過剰摂取と脂肪蓄積に深く関わっているのが、膵臓から分泌されるホルモン「インスリン」です。糖質を多く含む食事をすると、血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が上昇します。特に食後30〜90分の間に血糖値はピークを迎えます。これに反応して膵臓がインスリンを分泌し、血中のブドウ糖を全身の細胞に取り込ませることで血糖値を正常な範囲に戻そうとします。
インスリンの主な役割は「血糖値を下げること」ですが、実はそれだけではありません。インスリンは同時に、血液中の中性脂肪を脂肪細胞に取り込ませる働きも持っています。つまり、糖質を過剰に摂取すればするほど、インスリンの分泌量も増え、その結果として脂肪細胞が中性脂肪をどんどん吸収・蓄積する環境が整ってしまうのです。
加えて、糖質と一緒に脂質を摂ると、糖質によるインスリン分泌の影響を受けて、脂質もより脂肪として定着しやすくなります。つまり、糖質の摂りすぎは、それ単体で脂肪に変わるだけでなく、同時に摂った脂質の「太りやすさ」も高めてしまうのです。
このように、糖質はエネルギー源として欠かせない栄養素である一方で、摂取のバランスを欠いてしまうと、脂肪の蓄積を促進する原因となってしまいます。現代の食生活では、白米・パン・お菓子など糖質を過剰に摂りやすい環境にあるため、自分がどれだけ糖質を摂っているか、どのタイミングで摂っているかを見直すことが、健康維持や体重管理の第一歩と言えるでしょう。
食事量のコントロールとカロリー管理の重要性
五大栄養素とは、私たちが健康的な生活を送るために欠かすことのできない栄養素であり、「炭水化物」「たんぱく質」「脂質」「ビタミン」「ミネラル」の5つがそれに該当します。これらのうち、実際に身体のエネルギー源、つまり“カロリー”として体内で使われる栄養素は、「炭水化物」「たんぱく質」「脂質」の3つです。
それぞれのカロリーは次のように定められています。
炭水化物は1gあたり約4kcal、たんぱく質も同じく1gあたり約4kcal、そして脂質は1gあたり約9kcalと、他の栄養素と比較してエネルギー量が多くなっています。
これらを摂取することで、日々の活動や基礎代謝に必要なエネルギーが供給されます。
体重を落とす、つまり減量を目指す場合、基本的な考え方は非常にシンプルです。
それは「摂取カロリーが消費カロリーを下回る状態(摂取カロリー < 消費カロリー)」を継続的に作り出すことです。
このエネルギー収支のマイナス状態が続くことで、身体は不足したエネルギーを補うために脂肪を燃焼し、体重の減少へとつながっていきます。
そのため、日々の食事の中で摂取カロリーをコントロールすることが非常に重要になります。
たとえば、定食のように主食・主菜・副菜がバランスよく揃った食事においては、主食である「ご飯」の量を調整することがカロリーを抑えるための一つの有効な手段になります。
ご飯には炭水化物(特に糖質)が多く含まれており、それに伴ってカロリーも高めです。したがって、茶碗一杯のご飯を“普通盛り”ではなく“少なめ”にするだけでも、1回の食事で数10〜100kcal程度のカロリーダウンにつながることがあります。
ただし、ここで注意が必要なのは「ご飯の量を減らしたからといって、他のおかずやデザートでその分を補ってしまっては、結局のところ総摂取カロリーは変わらない、むしろ増えてしまう可能性がある」という点です。
たとえば、ご飯を半分にした後に甘いスイーツや高脂質なデザートを食べた場合、そのデザートのカロリーが思っている以上に高ければ、ご飯を減らしてマイナスになったカロリーが帳消しになる、もしくはプラスになることすらあります。
ただし、そのデザートの摂取も含めて自分自身の1日の総摂取カロリーを計算したうえで、「この食事ではご飯を控えめにして、その分後で○○を楽しもう」といったように、自分の食べている量を意識的に把握・調整して行動しているのであれば、それは非常に健全な栄養管理の一環だと言えます。
単に食事を我慢するのではなく、「食べる内容を選び、量を調整し、全体のバランスを整える」という考え方こそが、長期的に見て健康的かつ無理のない体重管理やボディメイクにつながるのです。
糖質を減らすなら、たんぱく質の摂り方にもバランス感覚を
糖質を控える、いわゆる「低糖質」な食事法は、体重を減らすための手段のひとつとして広く知られています。確かに、糖質は炭水化物の一種であり、1gあたり約4kcalのエネルギーを持つ栄養素であるため、これを食事から減らすことで総摂取カロリーを抑えることができ、その結果として体重減少につながる可能性があります。しかし、糖質を減らす食事を継続することで、ある傾向が現れることがあります。それは、「糖質を減らした分、たんぱく質をたくさん摂るようになる」という行動の変化です。
たんぱく質は私たちの身体を構成する非常に重要な栄養素であり、筋肉だけでなく、肌、髪の毛、内臓、血液、さらにはホルモンや酵素など、身体の構造や機能に関わる多くの成分の材料となります。特に、運動や筋トレを習慣にしている人にとって、筋肉を減らさないようにするためには、十分な量のたんぱく質摂取が必要不可欠です。ですから、糖質を控えている状態で「たんぱく質なら多めに摂っても問題ない」と考えることは、筋肉を維持するという観点からすれば、一見正しい判断にも見えるかもしれません。
しかしながら、このような「糖質は悪、たんぱく質は善」といった極端な見方には注意が必要です。たしかに、糖質が不足すると、身体はエネルギー源として脂肪を使い始めますが、それだけではなく、筋肉を分解してエネルギーを作り出す「糖新生」という代謝プロセスも活性化されてしまいます。つまり、糖質を極端に制限すると、筋肉量の減少が起こるリスクが高まるのです。これを防ぐためにたんぱく質をしっかり摂ることは大切なのですが、問題はその摂取量です。
たんぱく質もまた、炭水化物と同様に1gあたり約4kcalのエネルギーを持っており、摂取しすぎれば余剰分は脂肪として体内に蓄積されてしまいます。身体の材料となるからといって無制限に食べてしまえば、それはやがてカロリーオーバーとなり、体重の増加、場合によっては体脂肪の増加につながる可能性があるのです。
もちろん、筋トレや有酸素運動などの身体活動量が十分にあり、日常的にしっかりとしたトレーニングを行っている人であれば、摂取したたんぱく質は筋肉の合成に使われ、結果的に筋肉量の維持・増加につながるという前向きな影響が期待できます。しかし、もし運動量が少ないにもかかわらず、「糖質は悪いから」と安易に糖質を制限し、その代わりにたんぱく質を過剰に摂取してしまっている場合、それは逆に健康や体型にとってマイナスに働くことになりかねません。
重要なのは、「糖質を減らしたい」という目的がある場合でも、その背景にある自分のライフスタイルや活動量、摂取エネルギーのバランスをしっかりと理解したうえで栄養管理を行うことです。たとえば、日常的にたんぱく質を意識して摂るようにし、その結果として1日の必要量がしっかりと満たされている状態で、なおかつ自然と糖質の量も控えめになっているようであれば、それは身体にとってバランスの取れた食事法だと言えるでしょう。
無理に糖質を極端に減らすのではなく、たんぱく質・脂質・糖質のそれぞれが適切なバランスで存在してこそ、健康的かつ持続可能なボディメイクやダイエットが可能になります。食べることは生きること、そして身体をつくる行為です。だからこそ、一つの栄養素に偏ることなく、「どの栄養素も必要で、重要である」という前提を忘れずに、日々の食生活を整えていくことが大切です。
糖質制限よりも大切なのは食生活全体の見直し
体重を減らすための方法として、「糖質を控える」というアプローチは非常に分かりやすく、実践しやすい手段のひとつです。糖質、つまり炭水化物は、摂取されると体内でブドウ糖に分解され、主に血中、肝臓、筋肉にグリコーゲンという形で蓄えられます。このとき、グリコーゲン1gにつき約3gの水分が一緒に蓄積されるため、糖質を控えることで体内の水分も同時に減少します。その結果、体重が目に見えて減るという現象が起こりやすくなります。
さらに、糖質の摂取量が減少すると、エネルギー源として使われていたブドウ糖が不足するため、身体は肝臓や筋肉に蓄えられたグリコーゲンを分解してエネルギーを得ようとします。このプロセスにより、短期間で体重が減っていくのです。いわゆる「結果が出やすい」「体重がすぐに落ちる」と感じるのは、糖質と一緒に水分も抜けていくこと、そしてグリコーゲンが消費されていくことが主な要因です。
しかし、この糖質制限をある程度の期間続けた後、通常の食事に戻す、つまり再び糖質を摂るようになると、身体はその糖質を血中ブドウ糖として利用し、一部は筋肉や肝臓にグリコーゲンとして再び貯蔵しようとします。さらに、それでも余った糖質は体脂肪として蓄積される可能性があります。この現象を「リバウンド」ととらえる人もいれば、「身体本来のエネルギー代謝の仕組みが正常に機能しているだけ」と解釈する人もいます。
ただし、ここで問題となるのは、糖質制限を行っている間に体内で起きていた変化が、その後の代謝に影響を及ぼす可能性があるという点です。前述したように「糖新生」という仕組みにより、筋肉量が減少してしまうことがあります。筋肉は、安静時にも糖質をエネルギーとして消費する“エンジン”のような役割を果たしています。つまり、筋肉量が減ることで、糖質を効率よく使う力が低下し、結果として糖質を摂取しても使い切れず、脂肪として蓄積されやすくなるという悪循環に陥る恐れがあるのです。
また、糖質の摂取が減ると、インスリンというホルモンの分泌量も自然と減少します。インスリンは血中のブドウ糖を細胞内に取り込む役割を担っていますが、その働きが長期間あまり使われなくなると、細胞がインスリンに反応しにくくなる「インスリン抵抗性」が高まる可能性があります。これが進行すると、血糖値をコントロールする力が低下し、将来的に糖尿病のリスクを高めることにもつながりかねません。もちろん、これは数日や数週間の糖質制限で起こるような単純な現象ではなく、数ヶ月以上にわたって極端な糖質制限を継続した場合に起こると考えられています。
こうした点から、糖質制限は短期間で体重を落とす目的では有効な手段のひとつであるものの、長期的な健康管理という観点から見ると、注意が必要な方法であるとも言えます。体重を減らすこと自体がゴールではなく、いかに健康的に減らし、その体重を維持し続けられるかという視点が重要です。
大切なのは、「糖質制限ありき」ではなく、自分の食生活全体を見直し、バランスの取れた食事を習慣づけることにあります。たとえば、以前は糖質中心の食事をしていて、ごはん、パン、麺類を満腹になるまで食べていた人が、糖質の摂取量を意識的に抑えるようになり、代わりにたんぱく質や野菜を取り入れたバランスのよい食事を摂るようになったとします。この変化は、単に糖質の量を減らしたというだけではなく、「食事全体の質が高まった」「満腹になるまで食べる習慣を見直した」という点で、より本質的な改善と言えるでしょう。
こうした新しい食習慣が日常的に継続できるようになることで、食べ過ぎや栄養バランスの乱れ、体脂肪の蓄積といった問題を根本的に解決し、結果的に“太りにくい身体”を作ることにつながるのです。
ケトジェニックダイエットとは?
私たちの祖先が生きていた時代は、現代のように豊富に食べ物を手に入れられる環境ではなく、特に糖質(炭水化物)を摂取する機会が少ない生活を送っていたと考えられています。
そのため、身体は糖質ではなく脂肪を主なエネルギー源とする代謝システムを発達させており、その中で重要な役割を果たしていたのが「ケトン体」です。
ケトン体とは、糖質の摂取量が1日50g未満に抑えられた状態で、肝臓が脂肪酸を分解して生成する物質であり、ブドウ糖の代わりに脳をはじめとする身体のエネルギー源として利用されます。
この仕組みを活用し、体内の脂肪を効率よく燃焼させて減量につなげようとするのが、「ケトジェニックダイエット」です。
近年では、ケトン体が脳細胞を酸化ストレスから守る働きがあるとする研究結果も報告されており、ダイエット効果だけでなく、認知症予防など健康面での利点にも注目が集まっています。
一方で、このダイエット法は非常に制限が厳しい点にも注意が必要です。
基本的には、1日あたりの糖質を50g未満に抑えるだけでなく、脂質の多い食事に偏らせる必要があります。
この状態で血中のケトン体濃度が高まることを「ケトーシス」と呼び、通常は3日〜1週間ほどでこの状態に入り、体重が減少し始めるとされますが、人によっては2週間〜1か月ほどかかる場合もあります。
さらに、ケトーシスに入るまでの過程で、吐き気・頭痛・イライラ・集中力の低下・体臭の変化など、身体にさまざまな副作用が現れることもあります。
このような反応が出るかどうかは個人差が大きく、すべての人に適しているわけではありません。
つまり、ケトジェニックダイエットは、身体に本来備わったエネルギー代謝の仕組みを活用して脂肪を減らすという点で有効な方法とも言えますが、同時に、糖を主なエネルギー源として働く身体にとっては非常時の代謝反応を無理に引き起こしている状態とも言えます。
このため、肯定的な意見と否定的な意見の両方が存在し、実施する際は慎重な判断が求められるダイエット法であると言えるでしょう。

まとめ
糖質は、ただ「太る原因」として切り捨てるべき存在ではありません。
私たちの身体や脳が正常に機能するために欠かせない、大切なエネルギー源のひとつです。
糖質制限は確かに体重を落とす手段として有効な側面もありますが、それは“手段”であって“目的”ではありません。
むしろ大切なのは、「糖質を抜くこと」ではなく、「糖質をどう摂るか」「どのように自分の生活に合わせてバランスをとるか」という視点です。
過剰摂取を避けつつ、必要なタイミングで適切に摂取することで、脳も筋肉もエネルギー不足に陥ることなく、健康的に体型を整えていくことが可能になります。
本質的な健康づくりは、糖質だけでなく、食事全体の質を見直すことから始まります。
糖質制限をきっかけに、自分自身の身体の仕組みや食習慣を深く理解し、無理なく続けられるバランスのとれた生活を築いていきましょう。
TRANSCENDでは、一人ひとりの状況に合わせて適したメニューを組んでいます。
通う頻度についても月2回、月4回、月8回の3つのプランから選択できるので、お気軽にご相談ください。















